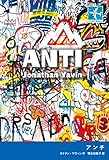- 作者: 蓼内明子(タテナイアキコ),大野八生(オオノヤヨイ)
- 出版社/メーカー: フレーベル館
- 発売日: 2019/09/09
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
出生の謎とか、芸術家気質で社会不適応気味の親といった素材には、目新しさはありません。それは逆にいえば、安心して読める素材であるということもでもあります。
冒頭のシーンが興味を引きます。ふみは読書仲間の孝太郎くんから「好きなんだ」と告白され、「たった今、孝太郎くんのこと、きらいになった」となります。他人から好意を持たれても嬉しいと思うとは限らず、ウザいとかめんどくさいとか思うこともままあるわけですが、このケースはなんなのだろうと先が気になってきます。
ふみと幼なじみのりょうとの関係もおもしろいです。ふたりとも一匹狼タイプでべたべたつるんだりはしません。でも、幼稚園時代からのつきあいで、オシッコで固めたという(嘘だったのだが)砂ダンゴを持たされて「ゲッ」となった思い出などを持っています。このつながりにより、それぞれの小6としての感性と幼年の感性に架け橋が生まれ、幼年を内部に抱えた存在としての人間の姿が浮かび上がってきます。
主人公の感性や脇役との関係性の描き方がうまく、全体としてよい雰囲気の作品になっています。
![きつねの橋 [ 久保田香里 ] きつねの橋 [ 久保田香里 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5603/9784035405603.jpg?_ex=128x128)



![空飛ぶくじら部 (カラフルノベル) [ 石川 宏千花 ] 空飛ぶくじら部 (カラフルノベル) [ 石川 宏千花 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8869/9784569788869.jpg?_ex=128x128)